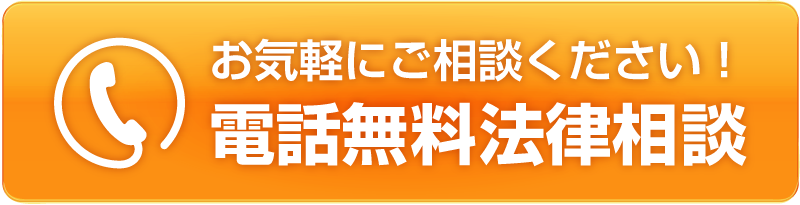2025年最新|会社法改正の論点は?
この記事を書いたのは:川村将輝


法務省が2024年9月から、商事法務研究会にて、会社法改正に向けた議論をスタートしています。今回予定される改正では、バーチャル株主総会の全面解禁やいわゆる実質株主確認制度の創設など実務上重要な論点が多く盛り込まれることが想定されています。
この記事では、今後の会社法改正の議論の状況について、先取りして解説します。
1. バーチャル株主総会・社債権者集会の制度化
近年、デジタル技術の発展やコロナ禍を契機に、株主総会のオンライン化が急速に進展しており、バーチャル株主総会(特にバーチャルオンリー型)の制度化が大きな論点となっています。これにより、従来は物理的会場の設営が必須だった株主総会を、完全にオンラインで開催することが可能となる方向で議論が進められています。
改正論点としては、通信障害時の対応(代替手段や議決権行使の保障)や議事の録画・録音義務、システム障害があった場合の決議取消し要件(セーフハーバーの導入)などが含まれています。また、社債権者集会についても同様に、オンライン開催の整備が検討されています。
これにより、全国に散在する社債権者に対しても公平な議決機会を提供することが可能となる。企業の代表者や取締役は、今後の定款整備やシステム導入に備える必要があります。また、総務・法務担当者には、実施要件や想定される法的リスクの把握、議事運営ルールのマニュアル化も求められるでしょう。
2. 実質株主確認制度の創設
株主名簿上の名義株主と、実際の議決権を行使する「実質株主」との乖離は、上場企業等におけるガバナンス上の課題として長年指摘されてきました。今回の改正論点では、名義株主に対して、実質株主情報の開示を請求できる制度の新設が検討されています。
企業はこれにより、議決権行使の背後にある実態を把握し、株主提案や敵対的買収への早期対応が可能となります。開示対象となる情報には、実質株主の氏名、議決権の数、株主との関係性などが含まれる見込みです。制度の実効性を担保するため、情報提供がない場合における議決権制限の可否も論点に挙がっています。
企業の代表者や法務・IR部門は、株主構成の透明化が進むことで、ガバナンスの強化とステークホルダーとの対話の質の向上が求められることになると考えられます。取締役や監査役にとっては、実質株主の存在を前提としたリスク管理や、説明責任のあり方に対する再整理が必要です。
3. 株式交付制度の拡張
2021年改正で導入された株式交付制度について、今後の会社法改正ではその適用範囲の拡張が議論されています。従来は、完全子会社化を目的とした一定の株式交付に限られていましたが、今後は子会社株式の一部取得や外国法人を子会社化する場合にも株式交付を利用できるようにする案が検討されています。また、上場会社が株式交付を行う際に、反対株主の株式買取請求権の付与を不要とすることも論点となっています。
これにより、株式対価M&Aの柔軟性が高まり、戦略的なグループ再編やクロスボーダーM&Aへの対応力が強化されることが期待されます。企業の代表者や法務部門は、M&Aスキーム選定において株式交付が現実的な選択肢となる場面が増えるため、実務上の影響や会計・税務面での整理を進める必要があります。また、株主対応やディスクロージャー方針も見直すことが求められます。
4. 現物出資規制の見直し
現行の会社法では、現物出資について厳格な規制が設けられており、特に500万円超の財産を出資する場合には検査役の調査が必要とされています。しかし、これが企業活動の柔軟性を阻害しているとの指摘を踏まえ、今後の改正では、取締役等による評価説明や外部専門家の証明により検査役調査を不要とする制度の導入が検討されています。
また、価額が著しく不足していた場合の引受人や取締役の責任についても、無過失責任とするか、過失責任とするかといった点が論点となっています。さらに、責任を問う際の評価時点について、「払込時」ではなく「募集事項の決定時」に変更する案も提起されています。
これにより、現物出資に関する事後的な責任追及の可否が明確になり、法的予見性が向上すると期待されます。企業の取締役や監査役にとっては、リスク評価と説明責任のあり方が変化することから、対応策の準備が必要です。
5. 従業員等への株式無償交付制度の法制化
人材の確保やモチベーション向上を目的として、従業員や役員に対して無償で自社株式を交付する制度が近年注目されています。これまで明確な法的根拠がなかったため、実務では第三者割当等の手法を工夫して対応してきましたが、今後の会社法改正では、株式無償交付制度の明文化が検討されています。
案としては、取締役会決議に基づき交付できる「包括的方針型(A案)」と、株主総会決議を必要とする「個別承認型(B案)」が提示されており、それぞれの法的安定性や手続の柔軟性が比較検討されています。この制度化により、企業はより制度的に安定した形で従業員インセンティブ制度を導入できるようになります。
法務担当者は、適切な社内規程や交付方針の策定を進め、誤解や法的リスクを回避するための透明な運用が求められます。
6. 株主提案権・質問権の見直し
株主提案権や質問権は、企業の説明責任やガバナンス強化において重要な制度ですが、昨今では形式的・大量の提案や質問が企業実務を逼迫するケースも見られます。特にバーチャル株主総会の導入が進む中、質問・提案の「事前提出方式」などを認めるか否かが論点となっています。
今後の改正では、一定の合理性をもって質問・提案の提出期限や回数制限を設けること、また会社が回答義務を負う範囲を限定することも議論されています。これにより、円滑な総会運営と少数株主の権利保護のバランスを図る制度設計が目指されています。企業の総務担当者にとっては、定款変更や運営ルールの整備、またFAQの事前準備など実務対応の強化が求められます。
また、代表者や取締役は、株主対応の透明性と公平性を意識した情報開示方針の見直しが必要です。
7. 新株予約権行使・設立時現物出資に関する規制見直し
現行の会社法では、現物出資に対して厳格な規制が設けられていますが、これは新株予約権の行使や会社設立時においても同様に適用されています。これにより、スタートアップや資本政策上の柔軟性が求められる場面で実務上の負担が大きくなっているとの指摘があります。
今後の改正では、これらの局面において、現物出資に係る検査役制度の適用除外や、外部専門家の評価証明による代替が提案されています。特に設立時の煩雑な手続きが緩和されることで、新規事業の立ち上げが容易になることが期待されます。
企業の代表者や法務担当者にとっては、資金調達手法の選択肢が広がる一方で、出資評価の妥当性や透明性をどのように担保するかが課題となります。リスク評価に基づいた実施体制の整備が必要です。
まとめ
今回の会社法改正論点では、社外取締役の義務化や指名・報酬委員会の強制設置といった直接的なガバナンス規制の強化には触れられていませんが、実質株主の透明化やバーチャル株主総会制度の整備など、実質的な統治構造の強化に資する施策が多く盛り込まれています。
これらは、改正コーポレートガバナンス・コードとの整合性を前提としつつ、上場企業のみならず中堅企業にも適用可能な制度設計が求められています。また、株式無償交付制度や現物出資規制の見直しにおいては、金融商品取引法、税法、会計基準など他法令との調和が重要な課題となります。企業の法務・総務部門は、会社法単体ではなく、横断的な法令理解のもとで制度変更に対応する体制を構築する必要があります。