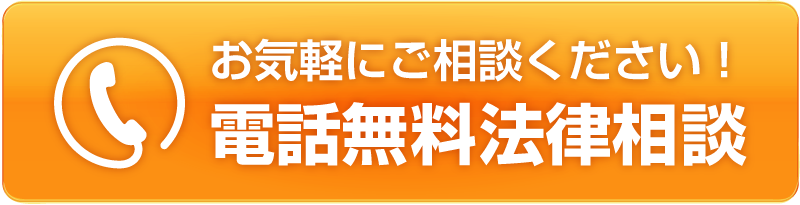宇宙法と航空法の違いを徹底解説【2025年最新版】
この記事を書いたのは:川村将輝

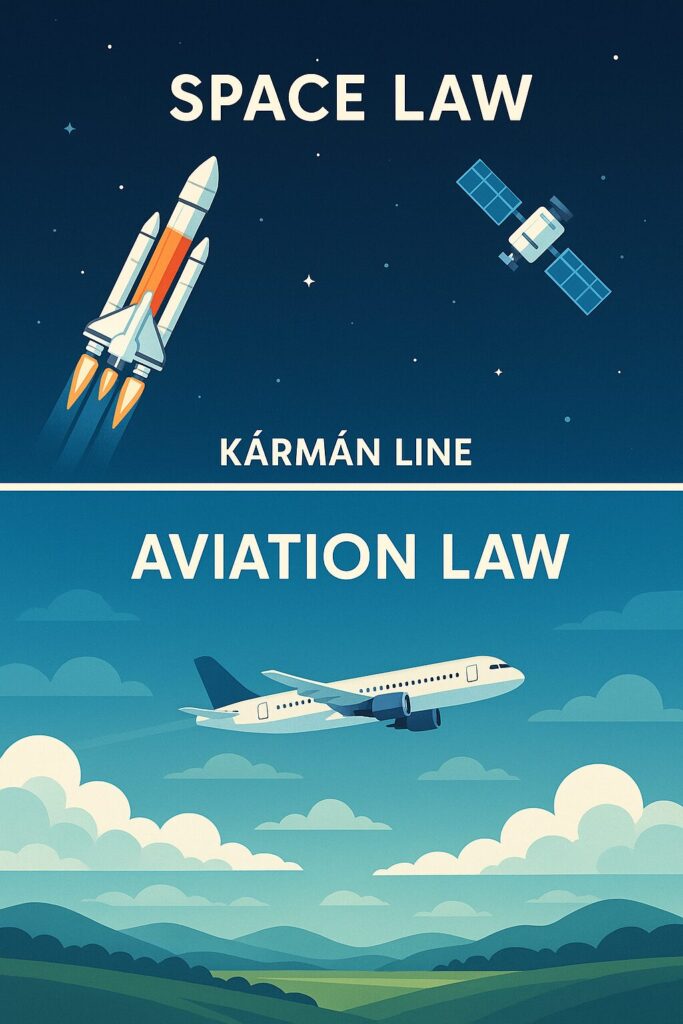
航空宇宙ビジネスが急速に成長する中、宇宙法と航空法の適用範囲を誤解することで生じる法的リスクが増加しています。現時点の法令では、例えばいわゆる準軌道飛行(サブオービタル飛行)ロケットについては、宇宙活動法の適用はありません。
というのも、宇宙活動法の制定当時、地球を周回する人工衛星等の打上げと比べれば、影響が及ぶ範囲が限定されているからとされます。しかし、現在は、このようなサブオービタル飛行を活用した様々な事業が現れ、民間企業における宇宙ビジネスの幅が急拡大しており、様々な法的グレーゾーンが実務上の大きな課題となっています。
本記事では、企業法務の観点から両法の違いを明確化し、実際のビジネス判断に必要な知識を提供します。
1. 宇宙法と航空法:基本概念の整理
1-1. そもそも「宇宙法」「航空法」とは何か
宇宙法の定義と特徴
宇宙法は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成28年法律第76号)(通称:宇宙活動法)を中心とする国内法と、1966年12月19日に採択された第21会期国連総会決議2222号で、1967年10月10に発効した宇宙条約などの国際法から構成されます。
宇宙条約は「宇宙の憲法」とも位置づけられ、宇宙活動に関する基本的なルールを定める条約です。その主要な規制対象は人工衛星、宇宙ステーション、宇宙探査活動であり、所管は内閣府宇宙開発戦略推進事務局、経済産業省等が担当しています。
航空法の定義と特徴
一方、航空法は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、並びに航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図ること等により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする法律です。
1-2. 法体系上の位置づけの違い
宇宙法は国際条約である宇宙条約を基礎として、各国が国内法を整備する構造となっています。宇宙空間における探査と利用の自由、領有の禁止、宇宙平和利用の原則、国家への責任集中原則などが定められていることが特徴です。
航空法は国際民間航空条約(シカゴ条約)に基づいて各国が整備しており、より成熟した法体系として長期間運用されています。規制アプローチとしては、航空法が安全重視、宇宙法が利用促進とのバランスを重視する傾向があります。
2. 決定的な境界線:高度と空域による区分
2-1. カーマンライン(高度100km)の意義
国際的なコンセンサスと日本の立場
カーマン・ライン(英語: Kármán line)は、海抜高度100キロメートル(62.1マイル)に引かれた仮想のラインである。国際航空連盟 (FAI) によって定められ、このラインを超えた先が宇宙空間、この高度以下は地球の気圏と定義されるとされています。
一般的には「地球の大気圏の外側が宇宙空間」とされますが、どこまでを大気圏とするかもとらえ方によって異なります。そのため、1950年代に宇宙開発が始まったときに国際航空連盟という民間団体が、地上から100kmを宇宙空間と大気圏の境界線と定義しました。
実務上の判断基準としての有効性と限界
しかし、カーマン・ラインは物理的なものではないので、もし誰かが高度100kmに達しても特に何も変化せず、カーマン・ラインに気づくこともないだろうという現実があります。
また、FAI(国際航空連盟)は宇宙との境界である高度100km、いわゆる「カーマン・ライン」の引き下げを検討しているそうですという動きもあり、最近公表された分析は、この高度を100kmから80kmにする説得力のある科学的材料を提示している状況です。
グレーゾーン事例:準軌道飛行、高高度気球
特に問題となるのが準軌道飛行(サブオービタル飛行)です。サブオービタルとは、周回軌道に乗るのではなく、打上げ後弾道軌道を描いて高度約100km付近を飛行するものをいいますが、サブオービタル機については、現在、わが国の法律上も、ロケットにも航空機にも分類できないまま、これを規制する適切な法律がない状況に置かれています。
2-2. 空域管理の違い
航空法による空域管理
航空法では、管制空域・非管制空域の概念に基づいて空域を管理し、航空機には飛行計画書の提出義務や航空交通管制との調整が求められます。これらの規制は地上から一定高度までの大気圏内での航行を前提としています。
宇宙活動における空域考慮
宇宙活動では、ロケット打上げ時の一時的な空域制限、衛星軌道と航空路の干渉回避、デブリ対策としての軌道管理が重要な要素となります。特に、宇宙物体登録条約に基づく宇宙物体の登録・管理義務が課されています。
2-3. 境界線が曖昧な新技術への対応
成層圏プラットフォーム(HAPS)、再使用ロケット・宇宙船、超高速輸送システムなど、従来の区分では対応が困難な新技術が登場しています。これらについては、国交省は、内閣府宇宙開発戦略推進事務局と合同で「サブオービタル飛行に関する官民協議会」を設立するなど、制度整備が進められています。
3. 規制内容・手続きの具体的違い
3-1. 許認可制度の比較
航空法における許認可
航空法では、以下の主要な許認可制度が確立されています:
- 型式証明:航空機の設計に対する安全性の証明
- 耐空証明:個々の航空機の安全性の証明
- 航空運送事業許可:旅客・貨物輸送事業の許可
- パイロットライセンス:操縦者の技能証明
これらは国際民間航空条約(シカゴ条約)に基づく国際標準に準拠しており、予見可能性の高い制度となっています。
宇宙活動法における許認可
宇宙活動法は、ロケットや人工衛星の打上げについて許可制度とすることで国が管理し、さらに打上げ事故に伴う賠償の指針を定めた内容となっており、以下の3点からなります:
- 人工衛星等の打上げ許可(宇宙活動法第4条)
- 人工衛星の管理許可(宇宙活動法第26条)
- 宇宙活動実施計画の認定(宇宙活動法第6条)
重要な適用除外: ただし、サブオービタルロケットについては、宇宙活動法の適用はありません。というのも、宇宙活動法の制定当時、地球を周回する人工衛星等の打上げと比べれば、影響が及ぶ範囲が限定されているからとされます。
実務上の連絡先:
- 宇宙活動法:内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 宇宙活動法担当(電話番号:03-6205-7162)
- 航空法:国土交通省航空局安全部航空機安全課
3-2. 安全基準・技術基準の違い
航空法では、数十年にわたる運用実績に基づいて精緻な安全基準が確立されています。一方、宇宙活動法では、技術の急速な進歩に対応するため、より柔軟な基準設定がなされています。
検査・監督体制についても、航空法では国土交通省による定期的な検査制度が確立されているのに対し、宇宙活動法では事業者の自主的な安全管理を基本とする制度設計となっています。
3-3. 国際協調の枠組み
航空分野:ICAO(国際民間航空機関)体制
航空分野では、ICAOを中心とした国際標準化が高度に発達しており、相互承認制度も確立されています。
宇宙分野:各国宇宙機関・国連宇宙部の役割
宇宙分野では、この条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約に基づいて、各国が国内法を整備する構造となっており、国際的な統一基準の策定は発展途上にあります。
4. 責任・保険制度の重要な相違点
4-1. 損害賠償責任の範囲と性質
航空法:ワルソー条約・モントリオール条約体制
航空分野では、旅客・貨物損害の責任限定制度や地上第三者損害への対応について、長期間にわたって確立された国際的な枠組みが存在します。
宇宙活動:国家責任原則と民間事業者の関係
この条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間に物体を発射し又は発射を行わせる場合には、その物体の打上げ国である当該当事国が、その物体又はその構成部分が地表面、航空機又は宇宙空間において他の当事国又はその自然人若しくは法人に与える損害について国際責任を負うとされており、国家責任原則が基本となっています。
4-2. 強制保険制度の比較
航空機強制保険の具体的内容
- 対人賠償:1事故につき300億円以上(航空法第79条)
- 対物賠償:1事故につき20億円以上
- 旅客賠償:乗客1名につき3,000万円以上
宇宙活動における保険付保義務 宇宙活動法では、以下の保険付保が義務付けられています:
- 第三者損害賠償責任保険:打上げ許可申請時に付保証明が必要
- 保険金額:想定される損害額に応じて個別に設定
- 保険期間:打上げ準備開始から軌道投入完了まで
実務上の課題
- 宇宙保険市場の限定性(ロンドン市場が中心)
- 新技術に対するリスク評価手法の未確立
- 保険料率の高さ(打上げ費用の5-15%程度)
保険会社との交渉ポイント
- 過去の類似案件の実績データ提示
- 技術的安全対策の詳細説明
- 段階的な保険適用(地上試験→飛行試験→商業運用)
4-3. 実務上の契約条項への影響
免責・責任制限条項の設計、国際契約における準拠法選択、フォースマジュール条項の考慮事項について、それぞれ異なるアプローチが必要となります。
5. 新興ビジネスモデルにおける判断実例
5-1. 宇宙旅行・準軌道飛行
Virgin Galactic型:航空機からロケット分離
Virgin Galactic社は、機体が母船に吊り下げられた状態で水平に離陸し、一定の高度に達した時点で母船から分離してロケットエンジンにて上昇し、エンジン燃焼終了後に訪れる無重量状態を体感した後、水平着陸する航空機タイプを採用しています。
法的適用の複雑性:
- 水平離陸~母船分離まで:航空法の適用
- ロケット点火後:サブオービタルロケットについては、宇宙活動法の適用はありませんが、航空法の適用も明確ではない
- 高度100km付近:カルマンラインを超えるが、明確な法的枠組みが未整備
Blue Origin型:地上からロケット打上げ
Blue Origin社は、宇宙船となるカプセルと一体となったロケットが垂直に離陸し、一定の高度に達した時点でカプセルを切り離して無重量状態を体感した後、パラシュートにより着陸するロケットタイプを採用しています。
法的適用の現状:
- 宇宙活動法の制定当時、地球を周回する人工衛星等の打上げと比べれば、影響が及ぶ範囲が限定されているから宇宙活動法は適用されない
- 航空法99条の2は、原則としてロケットの打上げを禁止しつつ、限定された場合にのみ得られる国土交通大臣の許可に基づき打上げを認めています
- 実務上は個別の許可申請により対応
5-2. 小型衛星・キューブサット事業
大学・研究機関による打上げ 宇宙活動法では、大学等の研究機関による小型衛星打上げについて手続きの簡素化が図られています:
- 簡易手続きの対象:重量50kg以下の研究目的衛星
- 審査期間の短縮:標準的な許可申請より短期間での審査
- 費用負担の軽減:許可申請手数料の減額措置
商用コンステレーション 大量の小型衛星を打上げる商用コンステレーションでは、以下が課題となっています:
- 個別許可の負担:衛星1機ごとの許可申請が原則
- 軌道調整の複雑化:既存衛星との干渉回避
- デブリ化防止措置:ミッション終了後の軌道離脱計画
外国からの委託打上げ 輸出管理法制との関係で以下の検討が必要です:
- 外為法:技術提供に関する許可(役務取引許可)
- 輸出貿易管理令:衛星本体や部品の輸出許可
- 打上げサービス:外国衛星の日本からの打上げに関する規制
実務チェックリスト □ 衛星の重量・用途による手続き区分の確認 □ 軌道投入計画の技術的妥当性検証 □ 第三者損害賠償責任保険の付保 □ 外国関連技術の輸出管理法制適合性確認 □ デブリ化防止措置の具体的計画策定
5-3. ドローン・無人航空機の境界事例
高高度長時間飛行ドローン
成層圏での長期滞空を行うドローンについては、航空法の適用限界が問題となり、準宇宙活動としての位置づけが検討されています。
宇宙からの大気圏再突入型デバイス
宇宙ステーションからの投下実験や再突入時の航空法適用可否について、新たなガイドラインの策定が必要な状況です。
6. 企業実務における注意点と対策
6-1. 事業計画段階でのリスク把握
法的適用関係の早期確定
技術的仕様と法的分類の整合性確認、複数法域にまたがる場合の調整方針、将来的な事業拡張への対応可能性を事前に検討することが重要です。
許認可取得スケジュールの現実的な設定
航空法では型式証明や耐空証明の取得に相当な期間を要し、宇宙活動法では人工衛星等の打上げ許可申請から許可まで相応の審査期間が必要となります。具体的な期間は個別の案件により大きく異なるため、事前に所管官庁との事前相談を行い、事業計画には十分な余裕を持った設定が必要です。
実務ポイント:
- 航空法:国土交通省航空局への事前相談(型式証明の場合は設計段階からの相談が重要)
- 宇宙活動法:内閣府宇宙開発戦略推進事務局への事前相談(TEL: 03-6205-7162)
6-2. 契約実務上の考慮点
サプライチェーン契約での責任分界
部品供給者の責任範囲明確化や適用法令の相違による責任格差への対応が重要です。
具体的な検討事項:
- 航空機部品:航空法に基づく耐空性基準への適合責任
- 宇宙機器部品:宇宙環境耐性や軌道上性能に関する責任
- 汎用部品の法的位置づけと責任分担の明確化
国際共同事業における準拠法・裁判管轄
多国籍企業間の宇宙プロジェクトでは、政府間協定と民間契約の調整が必要となります。実務上の注意点としては、下記のようなものが挙げられます。
- 宇宙条約第6条に基づく国家責任原則との整合性
- 各国の宇宙活動法制の相違への対応
- 技術輸出管理規制(EAR、ITAR等)の考慮
- 保険・損害賠償条項の国際調整
6-3. コンプライアンス体制の構築
社内での法的知識の共有体制、外部専門家との連携体制、法改正への継続的な対応仕組みの整備が不可欠です。
7. 今後の法制度動向と企業への影響
7-1. 法制度の一体化・調和化の動き
国交省は、内閣府宇宙開発戦略推進事務局と合同で「サブオービタル飛行に関する官民協議会」を設立するなど、準軌道飛行に関する統一的な規制枠組みの検討が進められています。
7-2. 新技術への法的対応
AI活用による自律航行システムや宇宙エレベーター等の革新的輸送システムに対する法的枠組みの整備が課題となっています。
7-3. 企業が注目すべきポイント
規制緩和による新規参入機会の拡大と、国際競争力維持のための制度対応が重要な検討事項です。
まとめ
宇宙法と航空法の本質的違いは、適用高度(カルマンライン)、規制目的(利用促進vs安全重視)、国際的枠組み(新興分野vs成熟分野)にあります。企業実務では、事業の技術的特性を正確に把握し、適用法令を早期に確定することが重要です。
特にサブオービタル飛行等の新分野では法的グレーゾーンが存在するため、継続的な情報収集と専門家との連携が不可欠です。今後の制度整備動向を注視しつつ、適切なリスク管理体制を構築することで、航空宇宙ビジネスの健全な発展に貢献することができるでしょう。