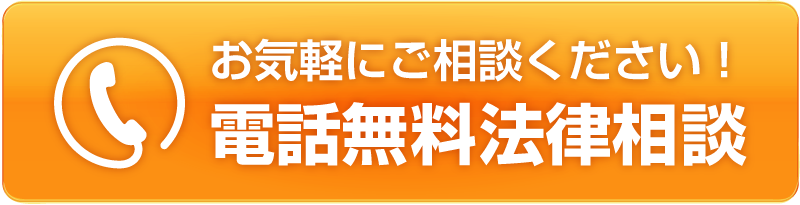宇宙デブリの法的責任 – 現状と課題|国際法の限界と新たな制度構築への道筋
この記事を書いたのは:川村将輝


はじめに
宇宙空間を漂う「宇宙ごみ」であるスペースデブリが、今や人類の宇宙活動にとって深刻な脅威となっています。2025年7月時点で観測されている軌道上物体は約54,000個。1cmから10㎝では120万個、1mmから1㎝では1.3億個以上と推定されています(米国宇宙戦略軍USSTRATCOM、ESAスペースデブリ事務局)。7〜8km/s程度で周回しているこれらのデブリは回収も困難であり、小さな破片でも運用中の衛星に壊滅的な損害を与える可能性があります。
宇宙デブリの法的責任をめぐる問題は、単なる技術的課題を超えて、国際法と宇宙ガバナンスの根幹に関わる重要な課題です。本記事では、現行の国際宇宙法制度の下でのデブリの法的責任、その限界、そして持続可能な宇宙利用に向けた新たな制度構築の必要性について詳細に検討します。
宇宙デブリとは? 深刻化する現状
宇宙デブリの定義と分類
宇宙デブリとは、機能していない人工物体及びその破片を指し、運用終了した衛星、ロケット上段、衛星の部品、さらには意図的な衛星破壊実験によって生じた破片まで含む広範な概念です。
デブリはサイズによって以下のように分類されます:
- 大型デブリ(10cm以上): 地上から追跡可能な程度のサイズ
- 中型デブリ(1cm-10cm): 衝突時に衛星を無力化する可能性があるもの
- 微小デブリ(1cm未満): 観測困難ですが累積的な損傷を与える可能性があるもの
宇宙デブリが引き起こす問題の深刻化
宇宙デブリの問題は年々深刻化しています。近年、イーロン・マスク氏率いるアメリカのSpaceX(スペースX)の衛星ブロードバンドサービス「Starlink(スターリンク)」を代表とする、衛星コンステレーションの構築に向けた打ち上げ数の急増によって、宇宙空間の混雑度が急速に悪化しています。
特に懸念されるのは「ケスラーシンドローム」と呼ばれる連鎖衝突現象です。これは、デブリ同士の衝突によって新たなデブリが大量発生し、さらなる衝突を誘発する現象で、最終的には特定の軌道帯が使用不可能になる可能性があります。
実際の衝突事例が示すリスク
2009年2月10日に発生した史上初の人工衛星同士の衝突事故は、この問題の深刻さを如実に示しています。米Iridium Satelite LLC社の保有するイリジウム33号とロシア宇宙軍が保有するコスモス2251号の両方が破壊されました(https://www.astroarts.co.jp/news/2009/02/13satellite_collision/index-j.shtml)。この衝突により、米宇宙監視ネットワーク (United States Space Surveillance Network; SSN) では500個以上のデブリを追跡中となり、軌道上の環境をさらに悪化させる結果となりました。
重要な点は、イリジウムの衛星はこの時点では稼働中であったということです。一方、ロシアの衛星は少なくとも1995年以降は運用されておらず既に活動停止中でした。つまり、廃棄された衛星が現役の商用衛星を破壊し、巨額の経済損失を発生させたのです。
宇宙デブリの法的責任に関する現行国際法
国際宇宙法の基本枠組み
宇宙デブリの法的責任を理解するためには、国際宇宙法の基本的な枠組みを把握する必要があります。現行の国際宇宙法は、主に以下の3つの条約によって構成されています。
1. 宇宙条約(1967年)
正式名称「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」は、宇宙法の根幹をなす基本条約です(1966年12月19日採択、1967年10月10日発効)。
第6条では以下のように規定しています:
「条約の当事国は、月その他の天体を含む宇宙空間における自国の活動について、それが政府機関によって行われるか非政府団体によって行われるかを問わず、国際責任を有し、自国の活動がこの条約の規定に従って行われることを確保する国際的責任を有する。月その他の天体を含む宇宙空間における非政府団体の活動は、条約の関係当事国の許可及び継続的監督を必要とするものとする。(以下略)・・・」
(出典:JAXA|宇宙条約)
この条項は、宇宙活動に対する国家の継続的責任を定めており、民間企業が宇宙活動を行う場合でも、その打上げ国が国際的な責任を負うことを明確にしています。
2. 責任条約(1972年)
宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約は、宇宙デブリの法的責任を考える上で最も重要な条約です(1971年11月29日採択、1972年9月1日発効)。
同条約は損害の発生場所に応じて異なる責任体系を採用しています:
地表での損害(第2条):
「打上げ国は、自国の宇宙物体が地表において引き起こした損害、又は飛行中の航空機に与えた損害につき無過失責任を負う。」
宇宙空間での損害(第3条):
「損害が、一の打上げ国の宇宙物体又はその宇宙物体内の人若しくは財産に対して他の打上げ国の宇宙物体により地表以外の場所において引き起こされた場合には、当該他の打上げ国は、その損害が自国の過失又は自国が責任を負うべき者の過失によるものであるときに限り責任を負う。」
(出典:JAXA宇宙法資料集 https://www.jaxa.jp/library/space_law/chapter_2/2-2-2-2_j.html)
この区別は、宇宙デブリによる損害の大部分が宇宙空間で発生することを考えると、立証責任の観点から重要な意味を持ちます。
3. 登録条約(1976年)
「宇宙空間に打ち上げられる物体の登録に関する条約」は、宇宙物体の識別と管轄権の確立を目的としています(1974年11月12日採択、1976年9月5日発効)。第2条では、打上げ国が宇宙物体を適切な国内登録簿に登録し、国連事務総長に通報することを義務付けています。
https://stage.tksc.jaxa.jp/spacelaw/world/1_01/01.J-4.pdf
現行法の適用における課題
故意によるデブリ生成への責任
2007年1月11日、中国が自国の気象衛星「風雲1号C」を弾道ミサイルで破壊する衛星攻撃兵器(ASAT)実験を実施しました。この実験により当時約650個のデブリが確認され、現在でも軌道上を周回しています。このような故意によるデブリ生成については、明らかに打上げ国(この場合は中国)の責任が問われるべきですが、実際には国際的な制裁や賠償は行われていません。
https://www.jaxa.jp/press/2007/02/20070207_sac_debris.pdf
偶発的デブリ生成の責任範囲
宇宙条約第9条の解釈に関する学説研究によれば、このような偶発的な衝突についても法的義務の適用可能性があることが明らかになっています。特に以下の点が重要です。
名古屋大学の松田芳和氏の研究によると、デブリの発生は「他国の利益に妥当な考慮を払う義務」の対象となり、適用に否定的な学説においても「適用の可能性を一定程度認め、また適用の可能性に否定的であっても、デブリの発生防止が第1文の義務ではないとまで判断しているわけではない」とされています(出典:松田芳和「スペースデブリの発生防止に関する宇宙条約第9条の規律」環境法政策学会誌第26号、2023年)。
この事例では、運用中だったイリジウム衛星の運用者と、既に制御不能だったコスモス衛星の打上げ国であるロシアの双方に、「他国の利益に妥当な考慮を払う」義務違反の可能性が検討されることになります。
立証責任の困難性
宇宙空間でのデブリ衝突において過失責任を立証することは極めて困難です。デブリの追跡技術には限界があり、1mm以上は1.3億個以上存在すると推定される微小デブリについては、そもそも追跡自体が不可能です。
さらに、宇宙空間では地上のような交通ルールが存在せず、どちらの衛星が回避義務を負うべきかという基準も明確ではありません。このような状況下で、特定の主体に過失があったことを立証するのは現実的ではありません。
学術研究では、宇宙条約第9条の解釈において、従来の二元的な適用判断(適用するか否か)から、「どこまで適用可能とみなすか」という観点への転換が提案されています。松田氏の研究では、「デブリの発生は『有害な汚染』に発展する場合もそうならない場合もあるので、デブリが引き起こす影響の程度によって個別に第2文への適用性の判断をする余地が残されている」と指摘されています。
この解釈により、偶発的な衝突であっても、その結果生じるデブリの量や影響の程度に応じて、段階的に法的責任を判断する枠組みが可能になります。
各国の国内法制度とデブリ軽減への取り組み
日本の法制度:宇宙活動法の先進的アプローチ
日本は2018年に「人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律」(平成28年法律第76号、通称:宇宙活動法)を施行し、デブリ軽減に関して世界的にも先進的な法制度を構築しています(2016年11月9日成立、2016年11月16日公布、2018年11月15日施行)。
内閣府宇宙開発戦略推進事務局によると、宇宙活動法における「人工衛星等の打上げに係る許可」及び「人工衛星の管理に係る許可」に関する審査においては、スペースデブリの発生防止策を具体的に確認することが規定されています(出典:内閣府「安全で持続的な宇宙空間を実現するための手引書について」)。
https://www8.cao.go.jp/space/application/other/guidebook.html
具体的には、同法に基づく許可申請時に以下の事項が審査されます:
- ミッション終了後25年以内の軌道離脱計画
- デブリ軽減措置の実施計画
- 他の宇宙物体との衝突回避措置
さらに、内閣府宇宙開発戦略推進事務局は、人工衛星やロケットの開発・運用を行うことを計画している企業・大学等の関係者に向けて、スペースデブリの抑制に係る手引書を作成しています。この手引書は、民間事業者が具体的なデブリ軽減措置を実施するための実践的なガイダンスを提供しています。
アメリカの取り組み:宇宙軍とFCCの役割
アメリカでは、商業宇宙打上げ法において民間事業者にデブリ軽減措置を義務付けているほか、連邦通信委員会(FCC)が通信衛星の免許条件としてデブリ軽減要求を課しています。
特に注目すべきは、2020年にFCCが採択したデブリ軽減規則で、低軌道衛星については運用終了後5年以内の軌道離脱を義務付けました。この規則は、SpaceXのStarlinkのような大規模衛星コンステレーションにも適用されます。
ヨーロッパの取り組み:ESAのガイドライン
欧州宇宙機関(ESA)は、2008年に「宇宙デブリ軽減ガイドライン」を策定し、加盟国および民間事業者に対してデブリ軽減措置の実施を求めています。このガイドラインは、国連の宇宙デブリ軽減ガイドラインの基礎となりました。
フランスでは、宇宙活動法において事業者にデブリ軽減義務を課しており、技術基準への適合性を審査する制度を導入しています。
民間企業による技術開発と法的課題
アストロスケールによる世界初の大型デブリ除去実証
日本企業アストロスケールは、宇宙デブリ除去技術の実用化において世界をリードしています。2024年8月、同社はJAXAとの間で商業デブリ除去実証(CRD2)プロジェクトのフェーズIIの契約を約132億円で締結しました(出典:株式会社アストロスケールホールディングス プレスリリース、2024年8月28日)。
JAXAによると、商業デブリ除去実証は「深刻化するスペースデブリ問題を改善するデブリ除去技術の獲得と日本企業の商業的活躍の後押しの二つを目的とするJAXAの新しい取り組み」です(出典:JAXA商業デブリ除去実証ウェブサイト https://www.kenkai.jaxa.jp/crd2/)。
このプロジェクトでは、2009年に温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT)を打上げたH-ⅡAロケット上段(International designator: 2009-002J, Catalog Number: 33500)を対象として、実際のデブリ除去技術の実証を行っています。
2024年には画期的な成果が達成されました。アストロスケールの商業デブリ除去実証衛星「ADRAS-J」が、2024年11月30日にデブリまで15mの近距離まで近づくことに成功し、実際のデブリ除去作業に必要な技術的基盤が確立されました。
デブリ除去の法的課題
しかし、デブリ除去技術の実用化には重要な法的課題が存在します。
他国宇宙物体への除去行為の合法性
国際法上、宇宙物体は打上げ国の管轄権の下にあり、他国がこれを除去することは主権侵害にあたる可能性があります。宇宙条約第8条では「宇宙空間にある宇宙物体又はその乗員に対する管轄権及び管理権は、登録国が保持する。・・・」と規定されており、デブリであっても法的地位は変わりません。
除去失敗時の責任
デブリ除去作業中に失敗が発生し、対象デブリや周辺の宇宙物体に損害を与えた場合、除去作業を行った国や企業がどのような責任を負うかは明確ではありません。責任条約の適用により、除去作業を行った国が損害賠償責任を負う可能性がありますが、元々デブリであった物体への損害について賠償義務があるかは議論の余地があります。
国際協力と新たな法的枠組みの必要性
国連における議論の進展
国連宇宙平和利用委員会(COPUOS)では、宇宙活動の長期持続可能性(LTS)ガイドラインの策定を通じて、デブリ問題への対処を進めています。国連スペースデブリ低減ガイドラインは、技術的な推奨事項を示していますが、法的拘束力は有していません。
業界による自主規制の発展
民間宇宙産業の急成長に伴い、業界団体による自主規制の重要性が高まっています。国際宇宙機関間デブリ調整委員会(IADC)は、技術的なガイドラインの策定を行い、商業衛星事業者間でも協力協定が結ばれています。
しかし、自主規制には限界があり、特に新興国の宇宙参入や小型衛星の急増に対しては、より包括的な国際的枠組みが必要とされています。
責任制度の課題と解決策
保険制度の整備
現在の宇宙保険制度は、主に打上げリスクと運用初期のリスクをカバーしており、長期的なデブリ化リスクは十分にカバーされていません。持続可能な宇宙利用のためには、デブリ除去費用を含む包括的な保険制度の構築が必要です。
国際デブリ除去基金の創設
個別の責任追及が困難な現状を踏まえ、国際的なデブリ除去基金の創設が提案されています。この基金により、責任の所在が不明確なデブリや、除去の緊急性が高いデブリについて、迅速な対応が可能になります。
将来の法制度構想と技術発展への対応
宇宙交通管制システムの法制化
宇宙空間における「交通ルール」の確立は、将来的なデブリ問題の予防において極めて重要です。航空交通管制と類似のシステムを宇宙空間に導入することで、衝突リスクの大幅な低減が期待されます。
人工知能とデブリ除去の法的位置づけ
将来的には、AIによる自動デブリ除去システムの導入が予想されます。この場合、AI判断による除去作業の失敗について、どの主体が責任を負うかという新たな法的課題が生じます。
月・火星圏への拡大
人類の宇宙活動が月や火星圏に拡大するにつれて、これらの領域におけるデブリ管理の法制度も必要になります。月協定の限定的な批准状況を考慮すると、新たな国際的枠組みの構築が不可欠です。
結論:持続可能な宇宙利用に向けて
宇宙デブリの法的責任問題は、単なる技術的課題を超えて、人類の宇宙利用の持続可能性に直結する重要な課題です。現行の国際宇宙法制度は1960-70年代の宇宙開発環境を前提としており、商業宇宙活動の爆発的成長と技術革新に対応できていません。
特に重要なのは、事後的な責任追及から事前の予防措置へとパラダイムを転換することです。デブリ軽減措置の義務化、国際的な監視システムの構築、そして技術開発への積極的投資を通じて、宇宙環境の保護と利用の両立を図る必要があります。
日本は、アストロスケールのような先端企業と約132億円(税込)という大型投資によるデブリ除去技術の実証、そして宇宙活動法による先進的な法制度を通じて、この分野で世界をリードする立場にあります。この優位性を活かし、国際的な制度構築において主導的役割を果たすことが期待されます。