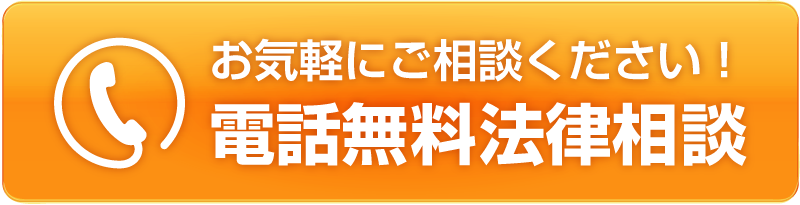【2025最新】宇宙活動法の改正動向をわかりやすく解説|民間宇宙ビジネスにも影響
この記事を書いたのは:川村将輝


宇宙開発競争に向けて
再使用型ロケット、宇宙旅行、サブオービタル飛行など、これまでの枠組みでは対応できなかった新たな宇宙活動が登場する中、法制度の見直しは喫緊の課題となっています。
2025年3月には、政府の宇宙政策委員会において「宇宙活動法の見直しの基本的方向性(中間とりまとめ)」が公表され、改正に向けた動きが本格化しています。本記事では、この改正の背景から最新の動向、企業への影響までを、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
宇宙活動法とは?その意義と課題
宇宙活動法(正式名称:人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律)は、2016年に制定され、2018年に施行されました。日本が初めて民間の宇宙活動を包括的に規律する法律であり、国際的な責任と安全性確保の観点から、打上げ・管理・損害賠償制度などを定めています。
しかし、施行から数年の間に宇宙ビジネスは大きく変化。再使用型ロケットや宇宙往還機、サブオービタル飛行といった多様な形態が登場し、現行法では対応が困難なケースが増えてきました。また、打上げ回数の増加に伴い、許認可の迅速化や手続の簡素化も求められるようになっています。
改正の背景:制度が現実に追いつかなくなっている
2023年の宇宙基本計画では、宇宙活動法の見直しについて「速やかに対応すべき課題」と位置づけられました。その背景には以下のような動きがあります。
- スペースXなど民間企業の再使用ロケットが実用化
- 有翼機による宇宙往還(往復)を目指す事業が日本でも進行
- 気球からの打上げや宇宙空間でのデブリ除去といった新技術
- 日本企業によるコンステレーション衛星の大量打上げ
- 宇宙旅行を見据えた有人宇宙飛行計画の始動
これらの活動は、現行法で定める「人工衛星の打上げと管理」の範囲に必ずしも収まりません。法制度が実態に追いついていないことが、ビジネスの制約や国際競争力低下を招くと懸念されてきました。
宇宙活動法改正に向けた議論の経緯と主なポイント
宇宙活動法の改正に向けた検討は、政府の宇宙政策委員会において2024年秋から本格化しました。特に内閣府の「宇宙活動法の見直しに関する小委員会」が2024年9月に設置されて以降、民間企業・有識者を交えた議論が重ねられ、2025年3月に中間とりまとめが公表されています。
以下は、委員会の議論の流れを時系列でまとめたものです。
| 開催日 | 回数 | 主なテーマ | 主要登壇者・内容 |
|---|---|---|---|
| 2024/9/26 | 第1回 | 小委員会発足、現行制度の課題共有 | JAXA、三菱重工、インターステラ社等によるヒアリング |
| 2024/10/1 | 第2回 | 再使用型ロケット・宇宙往還機 | ElevationSpace、STS社、兼松等が現場の課題を提示 |
| 2024/10/24 | 第3回 | サブオービタル飛行 | SPACE WALKER、PDエアロ社による有人宇宙飛行構想の紹介 |
| 2024/10/31 | 第4回 | 宇宙空間の安全性・損害賠償 | アストロスケール、商社などによる第三者被害リスクへの提言 |
| 2024/12/17 | 第5回 | 宇宙ビジネスの制度的支援 | 経団連、Synspective社による規制緩和の必要性提示 |
| 2024/12/19 | 第6回 | 有人宇宙飛行と旅客輸送制度 | 宇宙旅客輸送推進協議会、Space Port Japanが提言 |
| 2025/1/20 | 第7回 | 中間とりまとめ案の素案提示 | 方向性の合意形成に向けた議論 |
| 2025/1/29 | 第8回 | 中間とりまとめ案の確定 | 内容の最終調整と公表に向けた整理 |
この一連の議論から浮かび上がった主な論点は次の3つです。
ポイント①:制度対象の拡張(新たな宇宙活動への対応)
現行法では対象とされていなかった「再使用型ロケット」「宇宙往還機」「サブオービタル飛行」など、新たな技術に対する制度的な受け皿の必要性が共有されました。特に宇宙旅行や気球を用いた打上げなど、前例のない活動が国内でも計画されており、法整備なしでは実現不可能といえます。
ポイント②:ビジネス促進のための許認可合理化
民間企業の意見を反映し、打上げや衛星運用の許可をより簡素かつ迅速に行える制度設計が求められました。これにより、頻繁に衛星を打ち上げるコンステレーション事業や、複数回の実証実験を想定した開発段階のロケットなどが実行しやすくなります。
ポイント③:安全・補償体制の強化
宇宙機や人工衛星の落下事故に備えた損害賠償スキーム、政府補償制度の見直しも重要テーマとなっています。特に、事故発生時の第三者被害への補償や、事故報告義務の新設は、安心して宇宙活動を行うためのインフラとして注目されています。
最新情報:中間とりまとめ案のポイント
2025年3月に公表された中間とりまとめ案は、宇宙活動法改正に向けた実質的な指針を示すものとして、今後の立法作業に大きな影響を及ぼす内容です。以下の4つの柱に沿って、具体的な方向性が提示されています。
多様な宇宙活動への対応
再使用型ロケットの打上げと着陸、宇宙往還機の帰還、気球や飛行機からの打上げなど、これまで制度の空白地帯だった技術に対して、明確な規制枠組みを整備します。サブオービタル飛行や有人宇宙旅行といった近未来のビジネスも、制度内で実現可能になるための第一歩となります。
許認可制度の合理化
複数回の打上げを1つの許可でカバーする「包括許可制度」や、人工衛星の設計・構造をあらかじめ認証する「型式認証制度」を導入する方向で検討されています。これにより、事業者の事務負担軽減や打上げスケジュールの柔軟化が期待され、ビジネス機会の拡大につながります。
安全性・信頼性の確保
人工衛星やロケットの事故時における損害賠償の制度や、政府による補償の対象拡大が盛り込まれました。また、第三者被害が発生した場合の事故報告義務を新たに制度化することも想定され、安全・安心な宇宙活動の基盤を整備します。
宇宙産業の国際競争力の強化
日本人・日本法人が国外で行う宇宙活動についても一定の規律を及ぼす「域外適用」の拡大が検討されています。また、制度全体を国際的な標準と整合させることで、日本企業がグローバル市場で不利にならないよう配慮されます。
宇宙ビジネスへの影響とは?
宇宙活動法の改正は、宇宙ビジネスの実務に大きな影響を及ぼします。とりわけスタートアップやベンチャー、また海外展開を視野に入れた企業にとっては、次のようなメリットと注意点が存在します。
スタートアップの参入促進
開発段階の試験打上げも法制度の対象に含まれることで、これまで制度外だった小規模ロケットや実証実験が法的に支援されやすくなります。これにより、資金調達や事業スケールの観点からも、スタートアップにとって追い風となるでしょう。
海外事業との連携強化
日本企業が海外射場を用いて行う打上げや、海外企業との共同ミッションにも日本の法制度が柔軟に対応できるようになります。たとえば、宇宙往還機「ドリームチェイサー」を日本に帰還させる計画など、国際プロジェクトの促進が期待されます。
宇宙旅行や旅客輸送への道筋が整備
サブオービタル飛行や宇宙旅客輸送など、新たな移動手段としての宇宙輸送に法的な道筋がつけられることで、観光・交通インフラとしての宇宙利用が現実味を帯びてきます。搭乗者の安全確保や責任関係についても、先進国の制度を参考に構築される予定です。
保険制度と補償リスクの明確化
打上げ失敗や事故時の責任分担が整理され、政府補償制度の適用範囲も拡大することで、事業者にとってのリスクが軽減されます。同時に、適切な保険加入やリスク管理体制の整備が求められるため、法改正に伴うコンプライアンスの強化も必要になります。
今後のスケジュールと展望
中間とりまとめを経て、政府は今後、最終とりまとめを行い、2025年度内にも宇宙活動法改正案を国会に提出する可能性があります。法案が可決されれば、2026年以降の施行を視野に入れ、関係府省や企業は制度対応を本格化させることになります。
また、今回の改正は単なる法文修正ではなく、宇宙基本計画や産業政策とも深く結びついた「宇宙戦略」の一環です。国際競争が激化する中、日本の宇宙産業が遅れを取らないためにも、機動的な法制度の整備が不可欠です。
まとめ:改正の最新情報を継続的にチェックしよう
2025年現在、宇宙活動法の見直しは実質的な最終段階に入りつつあり、多様な宇宙活動と企業の挑戦を支える制度の構築が期待されています。
民間事業者にとっては、ビジネスチャンス拡大とともに、法的リスクや制度変更に伴う対応も求められます。今後の法改正の動向を適切にフォローし、専門家と連携しながら準備を進めることが、これからの宇宙産業に求められる姿勢といえるでしょう。