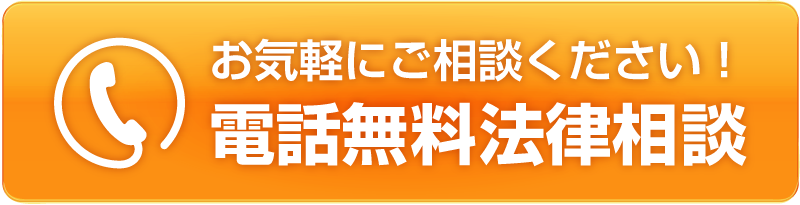グレーゾーン解消制度とは?見えないリーガルリスクを可視化し事業の競争力を得る活用法
この記事を書いたのは:川村将輝

「革新的な事業モデルを検討中だけど、法律に違反していないか不安…」という声は少なくありません。特に規制が複雑な領域では、新しいサービスやテクノロジーが既存の法制度と衝突することもあります。
そこで有効な方法が、「グレーゾーン解消制度」です。
本記事では制度の概要から活用事例、さらに外部専門家に依頼すべきかどうかの判断軸まで、法務未整備のスタートアップにもわかりやすく解説します。
グレーゾーン解消制度とは
新規事業に取り組む際、法律の解釈が明確でない領域、いわゆる「グレーゾーン」に直面することがあります。たとえば、既存の法制度が想定していない新しいテクノロジーやビジネスモデルに対し、「このサービスは違法ではないか?」といった疑念が生じるケースです。
こうした不安を抱える企業が、事業実施前に規制の適用有無について行政から正式な見解を得ることができるのが、「グレーゾーン解消制度」です。この制度は、2014年に施行された産業競争力強化法に基づいて創設され、現在は恒久的な制度として運用されています。
具体的には、企業が新事業の計画を提示し、その内容に対して関係省庁が「該当する規制が適用されるか否か」について公式に回答を行う仕組みです。たとえば、「このデータ分析サービスは医療行為に該当するか?」「この電子契約は建設業法上の契約書として認められるか?」といった問いに対し、主務官庁が事前に見解を出してくれます。
企業にとっては、規制の不確実性をあらかじめ解消することで、安心して新規事業を開始することが可能になります。また、投資家や業務提携先に対しても、行政からのお墨付きがあるという形でリスク説明がしやすくなり、信頼性の高いビジネス展開が期待できます。
制度の手続きと実務フロー
グレーゾーン解消制度の手続きは、大きく以下の流れで進みます。
-
事前相談(任意)
制度の利用にあたっては、まず経済産業省などの事業所管省庁に対して、非公開の事前相談を行うことが推奨されています。ここでは、事業内容や適用が不明な法令について意見交換を行い、照会文書の内容や論点を整理します。 -
照会書の提出
所定の様式に従って、事業内容や適用確認を求める法令の条文などを記載した照会書を提出します。提出先は、事業所管官庁(多くの場合、経済産業省)となります。 -
所管官庁による調整・審査
事業所管省庁は、関係する規制所管省庁(たとえば厚生労働省、国土交通省など)と協議を行い、照会内容に対して法令の適用有無を審査します。 -
正式回答の発出
通常、1か月以内を目安に、主務大臣名で正式な文書による回答が発出されます。内容は、「当該事業には○○法第△条は適用されない」といった形で明示されます。 -
回答結果の公表
回答内容については、企業の同意のもとで概要または全文が経済産業省のウェブサイト上で公表されます。他社にとっても参考になる事例として共有されるため、制度全体の透明性にも寄与しています。
注意点として、制度によって確認できるのは、あくまで特定の法令の「形式的適用の有無」であり、事業全体の適法性が保証されるものではありません。また、複数の法律が関連するケースでは、複数の所管省庁が関与することもあります。
専門家に依頼すべきか?社内対応との比較
グレーゾーン解消制度は、企業自身が申請主体となって活用する制度です。しかし、実際に制度を活用しようとすると、「どの法律が対象になるのか」「どの部分がグレーゾーンなのか」「どのように照会文を構成すべきか」など、多くのハードルに直面します。
とくにスタートアップ企業や法務体制が整備されていないベンチャー企業にとっては、制度の活用以前に、法的リスクの洗い出しや行政との対話の進め方に不安を感じることが多いのが実情です。
●こんな課題があれば、外部専門家への依頼を検討すべきです
-
自社サービスがどの法令に触れる可能性があるかを把握できない
-
行政に対して「何を」「どこまで」聞けば良いのか不明
-
社内に行政対応や法令解釈のノウハウがない
-
社外に対して「違法ではないこと」を裏付ける根拠が欲しい
こうしたケースでは、制度の形式的な手続きだけでなく、照会内容の設計そのものから外部の法律専門家に依頼することが望ましいと言えます。
●社内対応と弁護士依頼の比較
| 項目 | 社内対応(法務なし) | 弁護士に依頼した場合 |
|---|---|---|
| 法的リスクの洗い出し | 自力では困難。誤認リスクあり | 多面的に検討し網羅的に整理可能 |
| 照会内容の明確化 | 検討漏れ・表現ミスの恐れ | 目的に応じて戦略的に構成可能 |
| 行政への交渉 | ハードルが高く時間がかかる | 官庁対応に精通した弁護士が同席・代理も可能 |
| 公表リスクの見極め | 基準不明で対応が難しい | 公表事例に基づいたリスク評価が可能 |
| 他制度との比較検討 | 不可能に近い | ノーアクションレターや新事業特例との併用可否も含めて検討可能 |
グレーゾーン解消制度と弁護士の役割
弁護士に制度活用を依頼することには、大きく以下のようなメリットがあります。
1. 法的リスクの構造整理
新規事業に対して「どの法律が関わり得るか」「どの部分が規制の対象か」といった点を、契約法・業法・個人情報保護法・知財・労働法などの分野横断的に整理することができます。これは、いわゆる“社内でのなんとなくの判断”では対応が難しい領域です。
2. 照会内容の戦略設計
制度の本質は、「どの法律の、どの規定が、自社事業にどう適用されるか」をピンポイントで聞きに行くという点にあります。曖昧な聞き方をしてしまうと、回答も「個別事情による」といった抽象的なものになりかねません。
弁護士は、行政側の視点も踏まえた上で、明確かつ簡潔な照会文を構成することで、実効的な回答を引き出すことが可能です。
3. 官庁との信頼関係・交渉経験
特定の業法に通じた弁護士であれば、規制所管官庁との折衝経験を有しており、非公式な確認プロセスや実務運用の傾向についても熟知しています。これは、スタートアップ企業が単独で臨む場合と比べ、大きなアドバンテージになります。
4. 中長期的なレギュラトリー戦略支援
本制度で行政見解を得たあと、さらに「新事業特例制度」「規制のサンドボックス制度」などを併用することで、法改正につながるようなルール形成まで視野に入れた動きも可能になります。弁護士がパブリックアフェアーズ的な観点から支援できるかどうかも、依頼先を選ぶうえでの重要な指標になります。
まとめ
グレーゾーン解消制度は、イノベーションを阻害する「法的不確実性」を事前に取り除くための非常に強力なツールです。特に、新規性の高いプロダクトや既存制度に馴染まないサービスを検討するスタートアップ・ベンチャーにとっては、リスク低減だけでなく、投資家・顧客・行政への信頼構築にもつながる制度といえるでしょう。
一方で、実務上は、
-
どの法令が関係するかの精査
-
照会内容の明確化
-
官庁ごとの対応方針の把握
といった高度な検討を要します。
こうした観点からも、制度活用を本気で検討する企業こそ、弁護士などの法務専門家と連携して進めるべきです。
当事務所では、グレーゾーン解消制度の活用支援についても、初期の制度適用可能性診断から、照会文作成、官庁対応、制度活用後のリスク管理まで、総合的にご支援しています。まずは、お気軽にご相談ください。