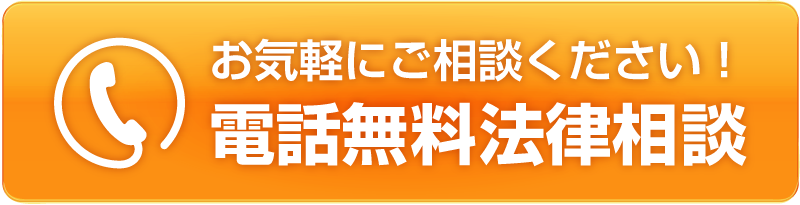損害賠償命令制度とは?
この記事を書いたのは:旭合同法律事務所(名古屋)

Q1 先日、居酒屋でお酒を飲んでいたところ隣に座っていた人とトラブルになり顔面を複数回殴打される等の暴行を受け、加療2か月程度の怪我を負いました。先日、検察官から連絡があり加害者は傷害罪で起訴されたようです。今回の事件で医療費等の財産的損害や相当の精神的苦痛を受けたので、加害者に損害賠償を請求したいと考えています。どのような手続きによって損害賠償を請求することができますか?

A 通常の民事訴訟手続きでも不法行為を理由として損害賠償請求をすることができますが、今回の事件では刑事手続に付随する損害賠償命令制度を利用することができます。
Q2 損害賠償命令制度とはどのような制度ですか?
A 損害賠償命令制度とは、刑事事件を担当した裁判所が、有罪の判決を言い渡した後に、引き続き当該事件に関する損害賠償請求についての民事の審理を行い、加害者に損害賠償を命じることができる制度です。

Q3 損害賠償命令制度は誰でも利用できますか?
A 損害賠償命令制度の対象犯罪の被害者本人又は被害者が死亡した場合における一般承継人(相続人など)が申立権者です(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(以下、「保護法」といいます。)24条1項柱書)。対象犯罪は、故意の犯罪行為により人を死傷させた罪、不同意わいせつ・不同意性交等罪、逮捕・監禁罪、略取・誘拐罪など(保護法24条1項各号)のいわゆる重大犯罪です。
Q4 損害賠償命令制度を利用できる期間に制限はありますか?
A 損害賠償命令の申立ては、当該事件が起訴されてから弁論終結に至るまでの期間に限り行うことができます(保護法24条1項柱書)。
Q5 損害賠償命令制度にはどのようなメリットがありますか?
A ①損害賠償命令制度では裁判所は原則として刑事事件の訴訟記録を取り調べなければならないとされています(保護法35条4項)。通常の民事訴訟では、被害者自ら被害に遭った事実が不法行為に該当することを主張立証する必要があります。しかし、損害賠償命令制度を利用する場合には刑事記録を流用することができるため主張立証に伴う負担を軽減することができます。
②審理が原則として4回以内に終結するため、簡易迅速な解決を期待できます(保護法35条3項)。
③損害賠償命令の申立てについての裁判は、口頭弁論を経ないですることができます(保護法34条1項)。非公開で審理がなされた場合には、被害者の公開に伴う精神的苦痛を軽減することができます。
④通常の民事訴訟では、例えば200万円の損害賠償を求める場合には1万5000円の手数料を支払う必要があります。これに対して損害賠償命令制度では、申立手数料が原則として2000円(保護法47条5項)であるため、通常の民事訴訟に比べて申立者の費用負担が軽くなります。

この記事を書いたのは:
旭合同法律事務所(名古屋)