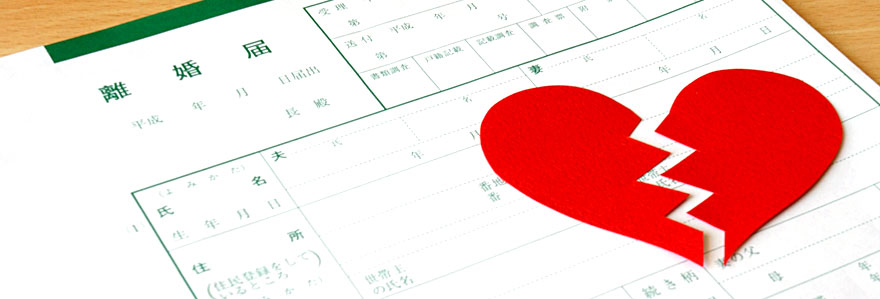
養育費の決め方
養育費の決め方は、離婚する当事者の合意によって決めるのが原則です。
ただし、当事者の話し合いが決着しない場合には、家庭裁判所の調停や審判によって解決することになります。
家庭裁判所では、養育費の算定を簡易化し、迅速な算定を実現するために、平成15年4月に東京・大阪養育費等研究会によって発表された「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」が活用されています。
この算定表は、その後の運用を踏まえて検討・改訂されていますので、実際の調停や審判においては非常に重要な役割を果たします。
この算定表は、当事者の総収入を基準とし、子の人数や年齢によって算定しています。
この算定表を使用した使用例を紹介します。権利者(母)が2歳の子を監護養育しており、単身の義務者(父)に対して、子の養育費を求める事例を考えます(これは大阪弁護士共同組合が作成した事例の紹介です)。
母は、給与所得者で、前年度の源泉徴収票上の収入は133万6382円、父も、給与所得者で、前年度の源泉徴収票上の収入は510万5573円となります。
この収入を基準として、算定表をみると、月額「4から6万円」の枠内となります。この枠内の金額を基準として、双方の個別事情を加味して最終的な金額を決定しています。
この算定表は、標準的な事案を前提にしていますので、個別の事情によって変動する可能性はあります。
たとえば、養育費の算定表は、子の生活費指数(親を100とした場合、14歳以下の子は55、15歳以上の子は90)を定めるに当たって、公立中学校、公立高等学校の学費を考慮していますが、私立学校の学費その他の教育費は考慮していません。
したがって、義務者が私立学校への進学を承諾している場合や、その収入及び資産の状況からみて義務者にこれを負担させることが相当と認められる場合には、養育費の算定にあたって、私立学校の学費等を考慮する必要があるとの見解があります(判例タイムズ1209号、10頁)。
個別の事案によっては、私立学校の学費が養育費の加算事情になることもありえます。
無職の元夫の養育費
養育費は原則として実収入を基礎として算定します。
無職の元夫の場合には、「ゼロ」として算定されることになります。
ただし、稼働能力があるのに収入を「ゼロ」として算定するのは不相当ですから、厚生労働省が策定した統計資料である賃金センサスなどを利用して、収入を推計して養育費を算定するケースもあります。
養育費と児童扶養手当
養育費の法律相談では、「児童扶養手当や児童手当を貰った分は、養育費から引かれますか」という相談もあります。
児童扶養手当や児童手当は、私的扶助の補助的意味が強いので、養育費の算定には無関係です。
ですから、養育費額から手当分が引かれることもありません。
決めた養育費の金額は代えられるの?
離婚に際しては、親権者の指定、養育費の金額、面会交流について協議して決めないといけないとされています。
養育費は子どもの年齢にもよりますが、長期間の給付になりますので、養育費を支払う親が将来どのような事態になるかは予想できません。
離婚に際しては、離婚時の夫婦の収入により養育費の金額が決められます。
しかし、離婚後養育費を支払う親がリストラに会い決めた金額を支払えなくなったり、養育費を受け取る側の親が再婚したりして別に子どもを扶養してくれる人ができたりすることもあります。
養育費は、当事者の状況で増減します。
事情としては、
1.父母の再婚、それによる新たな子の誕生
2.父母の職業の変更(失業など)と収入の変化
3.病気
4.子の成長や進学や就職
5.社会情勢、経済情勢
などが主たる事情になります。
増減の協議が成立しない場合には、調停、審判によって家庭裁判所で決めることが多いでしょうね。
そういう時は、養育費の減額を求めることになります。任意の交渉での減額が難しければ、養育費の減額調停をすることになります。
しかし、調停の当時、当事者に予測不能であったことが後で生じた場合に限り、これを事情の変更と評価して調停の内容を変更することが認められるため、例えば、大幅な給料の減収があったとしても、それが予測可能であった場合には、減額は難しいということになります。
減額が決まるまでは、従来の金額の養育費を支払う義務があります。
反対に養育費を支払う親の収入が増えたりした場合は、養育費の増額を請求できる場合もあります。
いったん養育費を決めても、その後の事情の変更により、増減が可能です。
再婚と養育費
離婚後、親権者である母親が再婚し、未成年の子供と再婚相手の男性が養子縁組をした場合、父親(実親)に養育費の支払い義務は残るでしょうか。
この場合、未成年者との養子縁組においては、養親は子の福祉と利益のためにその扶養を含めて全面的に引き受けるという意思の下に養子縁組をしたと認められるので、未成年者に対する扶養義務は第1次的には養親にあり、実親は養親が無資力その他の理由により扶養義務を十分に履行できないときに限って、第2次的に扶養義務を負うものと考えられています。
したがって、再婚相手の男性が未成年者と養子縁組をした場合、実親は原則として養育費の支払義務を負わないことになります。
ただ、実父親も扶養義務が劣後するだけで当然になくなるわけではなく、母親と再婚相手(養親)の経済状態等によっては、二次的な養育義務が生じますので、養育費の負担を全くしなくてよいということにはなりません。
母親が再婚した男性が子供と養子縁組していない場合には、父親が第一次的な扶養義務を負うことに変わりありません。ただ、その場合でも、事情の変更があるとして、養育費の減額請求が認められる可能性はあります。
実家の援助と養育費
離婚後の妻が実家で生活している場合、実家の経済的援助を受けていることが多いです。
そのとき、養育費の算定において夫側から「実家から援助を受けているので生活に困っていない」旨を主張して養育費の減額を述べられることがあります。
しかし、この養育費の減額は認められません。家庭裁判所では、実家からの援助は好意に基づく贈与であって、妻の「収入」に加算はしません。
過去の養育費の請求
夫婦の一方が、子どもを連れて別居した場合には、例外的な場合を除いて婚姻費用(本人と子供の生活費)の請求が可能です。しかし何らかの理由で婚姻費用を請求せずに離婚まで来てしまった場合は、どうなるのでしょうか。
最高裁は、離婚裁判で別居時から離婚時までの養育費の請求は可能であるとしています。したがって離婚裁判時に慰謝料や財産分与とともに過去の養育費も請求することになります。
なお別居後婚姻費用を受け取っている場合は、養育費が含まれていることになりますので、その間の養育費は請求できません。
養育費の不払があった場合の間接強制
養育費の不払があった場合の履行確保の方法として「間接強制」もあります。
判りやすく言えば、養育費の不払に対する金銭的制裁であり、養育費の支払いがない限り、たとえば、1日当たり1000円等の金銭負担を加えるものです。
養育費不払いの「倍返し」ともいえます。
裁判例では、1日当たり1000円とするもの、5000円とするもの等様々ですが、相手方の社会的地位、収入、資産等を考慮していると解釈されています。
養育費 子と面会交流できない場合
養育費等の支払義務者から、子供と面会交流ができないことを理由に養育費等の支払いをしない、したくないという主張をされることがあります。
しかし、子供と面会交流ができないとしても、扶養義務を免れるわけではありません。
そのため、子供と面会交流できないことが、養育費や婚姻費用の算定にあたって、考慮されることはないと言ってよいでしょう。


